yama_06.htm
私の山行日記
ちょっぴり山の名前と花の名前を覚えました。相変わらず無理せずのんびりと自然を謳歌しています。
(さて、次は何処の山へ行きましょうか?)
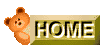
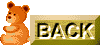
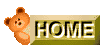
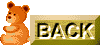
町田
6:33(JR横浜線・中央線)⇒
7:18高尾
(バス:宝生寺団地行)⇒7:30霊園前バス停⇒7:50八王子城跡入口8:10:⇒8:50城山(445.5m)八王子城跡
9:00⇒
9:50富士見台⇒
11:30荒井(昼食)12:10⇒12:45高尾駅
⇒13:10ふろっぴィ
昨日からの雨の中を雨が上がる事を期待して出発!今日の目的地!「るるぶ 大人の遠足BOOK:奥多摩・高尾を歩く」に載っていた北高尾山稜を歩く事にしました。歩行時間が5時間20分と掛かるものの低山である事であまり前準備も下調べもろくにせず小雨の中を決行! 高尾駅北口改札を出ると宝生寺団地行のバスが来ていたので飛び乗ると、すぐに発車。10分足らずで霊園前バス停に着きました。ここは八王子霊園や東京霊園といった大きな霊園がある為、墓石店が多く並んでいます。20分程歩いた所で八王子城跡入口に着きました。ここには管理棟やトイレもあるので、準備を整えたところで出発。
高尾駅北口改札を出ると宝生寺団地行のバスが来ていたので飛び乗ると、すぐに発車。10分足らずで霊園前バス停に着きました。ここは八王子霊園や東京霊園といった大きな霊園がある為、墓石店が多く並んでいます。20分程歩いた所で八王子城跡入口に着きました。ここには管理棟やトイレもあるので、準備を整えたところで出発。

弱い雨が降っていた為、山道に入ると薄暗く、思いの他急登で、景色を楽しむ事も出来ないままにもくもくと足を運びます。天守閣跡に辿り着いた時には汗だくでした。雨でジメジメしているせいか巨大ミミズ(太さ1cm、長さ40cm)が姿を見せたり、動物の骨らしきものがあったり何とも不気味な領域に入ってしまったと言う感じでした。
その後、富士見台までは地図どおり歩いたものの、ここからは地図とにらめっこしても道標 は持参の地図には出ていない場所を示すばかり。どれほど歩いたでしょうか、私たちは城跡の峰を数時間掛けて歩いていたようでした。
は持参の地図には出ていない場所を示すばかり。どれほど歩いたでしょうか、私たちは城跡の峰を数時間掛けて歩いていたようでした。
帰宅してから判った事ですが、私たちが道に迷い彷徨っていた場所は、結構話題になっていた心霊スポットだったようです。(ぞーっ)
 お腹もすいたので、高速道路が見えたところで里へ降りる事にしました。荒井と言う民家も立ち並ぶ中央線の線路沿いに出ました。丁度、梅林に椅子とテーブルが置いてあったので、許可を頂き、そこでお弁当を広げる事が出来ました。
お腹もすいたので、高速道路が見えたところで里へ降りる事にしました。荒井と言う民家も立ち並ぶ中央線の線路沿いに出ました。丁度、梅林に椅子とテーブルが置いてあったので、許可を頂き、そこでお弁当を広げる事が出来ました。
「何処で、道を間違えたのか」
「雨の日は辞めるべきだった」
「なんでこのコースを歩いたのか」
いろいろ反省する事しきり・・・
まあ!次回は・・・きっと晴れますよ!多分!良い事あるある!
2008年 7月19日(土)〜20日(日)
【1日目】
町田00:01(JR横浜線)⇒00:26八王子0:40(ムーンライト信州81号)⇒4:51穂高(タクシー)⇒6:00中房温泉
中房温泉(朝食)6:30⇒8:00第二ベンチ⇒9:40合戦小屋10:00⇒11:30燕山荘(昼食)12:30
⇒13:40燕岳(2,763m)⇒15:00燕山荘
【2日目】
燕山荘5:30⇒6:30合戦小屋7:15⇒10:00中房温泉(バス)11:25⇒12:20穂高(JR中央線)13:05
⇒13:34 松本(昼食:蕎麦)15:21(はまかいじ号)⇒18:14町田
初めてのアルプス挑戦に心躍らせて、ムーンライト信州に乗り込みました。このムーンライトと言う列車は寝台車ではないので熟睡は出来なかったものの、時間を効率よく使うのにとても都合の良い列車で、しかも安いのが魅力!
一番の気掛かりだった天候も私たちに味方してくれたようで、最高の山行になりました。可憐なコマクサも見頃を迎えており、とても珍しいとされる白いコマクサも見る事が出来ました。


 今回の山行にあたっては、体力的な事、家庭の事を含め実行出来るか迷いがありましたが、メンバーの一人に「行ける時に行かないと、来年行けると言う保障は無いよ」と言う言葉で、これまでの迷いは消えていました。登った後には素晴らしい景色を目に焼き付けた満足感と達成感で溢れていました。来年の事を言うと鬼がお腹を抱えて笑い出しそうですが、さて来年は・・・あたりを登ってみましょうか?
今回の山行にあたっては、体力的な事、家庭の事を含め実行出来るか迷いがありましたが、メンバーの一人に「行ける時に行かないと、来年行けると言う保障は無いよ」と言う言葉で、これまでの迷いは消えていました。登った後には素晴らしい景色を目に焼き付けた満足感と達成感で溢れていました。来年の事を言うと鬼がお腹を抱えて笑い出しそうですが、さて来年は・・・あたりを登ってみましょうか?
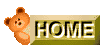
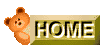
2009年 4月28日(火)
【コース】
町田7:28(JR横浜線)⇒7:54八王子(JR中央線)8:09⇒8:57大月9:10⇒9:40岩殿山丸山公園入口
⇒9:50岩殿山ふれあいの館⇒10:30岩殿山(634m)⇒11:00築坂峠 ⇒11:50天神山
⇒12:20稚児落し(昼食)13:00⇒14:10大月15:24 ⇒16:18八王子16:35⇒17:01町田
山行にしては遅い出発に不安が的中!八王子までの横浜線の混雑は尋常なものではありませんでした 。自分の体が自分で制御出来ないまま八王子までどうにか運ばれて行った感じの恐怖の数分間でした。次回はやはり早起き早出と皆が反省。
。自分の体が自分で制御出来ないまま八王子までどうにか運ばれて行った感じの恐怖の数分間でした。次回はやはり早起き早出と皆が反省。
大月駅に到着するとこれから登る岩殿山がすぐそこにそそり立っていました。改札は山とは反対側の1箇所しか無い為、改札を出て道標に従い左に曲がり踏み切りを目指します。30分ほど歩くと岩殿丸山公園入口に出ます。
整備された階段を暫く上がったところに「岩殿山ふれあいの館」があります。そこで情報を伺ったり地図など頂く事が出来ます。富士山も美しく拝む事が出来最高!!
ふれあいの館から40分程で岩殿山山頂に到着です。パラボラアンテナが立ち並び頂上らしからぬ頂上に少々ガッカリですが、今日の行程の半分も歩いていません。一旦分岐点に戻り、築坂峠を過ぎたところに今回一番の難所である鎖場を通過します。1つ目は足場もあり難なく登れました。次は幅10cm程のバンドを通過。鎖をしっかり掴み足元に注意してゆっくり渡ります。ここを通過すると最後の鎖場!ここは足場の確保が居難い。しっかりした手 袋が無いときついかもしれません。高所恐怖症や鎖場に慣れて無い方は、巻き道あるので心配はいりません。
袋が無いときついかもしれません。高所恐怖症や鎖場に慣れて無い方は、巻き道あるので心配はいりません。
その後、送電線の鉄塔を2つ過ぎた所で、100mは優に超すであろう巨大絶壁が現れます。あまりの凄さに暫く佇んでしまいました。そこから稚児落しの頂点で昼食を取る事にしました。崖の際まで行くと足が竦み、崖下は直視出来ませんでした。のんびり昼食を取った後、大月駅へ向う為稚児落しの先へ浅利公民館方面へ向けて歩きます。季節柄、竹林に目をやると筍が頭を覗かせていました。稚児落しから1時間余りで大月駅に着きました。電車の時間まで休憩を兼ねて、駅前の不二家でケーキとコーヒーを頂き至福の時を過ごしました。
今回の岩殿山は、低い割には歩きでがあり、変化に富んだ面白い山でした。
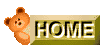
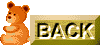
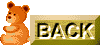
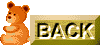




 下りは通称バカ尾根と呼ばれている大倉尾根を下ります。そこは変化に富んだ急坂なので足元に気を配り慎重にならざるを得ません。金冷シを下ってすぐの所で野性の鹿が数頭のんびり草を食んでいる所に出逢いました。山道のすぐ脇で沢山の人が居たにも拘らず、逃げる素振りもなく悠然とした鹿の姿は、この山は、自分達の縄張りであると主張しているかのように映りました。
下りは通称バカ尾根と呼ばれている大倉尾根を下ります。そこは変化に富んだ急坂なので足元に気を配り慎重にならざるを得ません。金冷シを下ってすぐの所で野性の鹿が数頭のんびり草を食んでいる所に出逢いました。山道のすぐ脇で沢山の人が居たにも拘らず、逃げる素振りもなく悠然とした鹿の姿は、この山は、自分達の縄張りであると主張しているかのように映りました。










 は持参の地図には出ていない場所を示すばかり。どれほど歩いたでしょうか、私たちは城跡の峰を数時間掛けて歩いていたようでした。
は持参の地図には出ていない場所を示すばかり。どれほど歩いたでしょうか、私たちは城跡の峰を数時間掛けて歩いていたようでした。 お腹もすいたので、高速道路が見えたところで里へ降りる事にしました。荒井と言う民家も立ち並ぶ中央線の線路沿いに出ました。丁度、梅林に椅子とテーブルが置いてあったので、許可を頂き、そこでお弁当を広げる事が出来ました。
お腹もすいたので、高速道路が見えたところで里へ降りる事にしました。荒井と言う民家も立ち並ぶ中央線の線路沿いに出ました。丁度、梅林に椅子とテーブルが置いてあったので、許可を頂き、そこでお弁当を広げる事が出来ました。






















 グラスの色合いを楽しみました。
グラスの色合いを楽しみました。









 鉄塔から更に30分ほど登った所にビリ堂が現れました。
鉄塔から更に30分ほど登った所にビリ堂が現れました。
 。自分の体が自分で制御出来ないまま八王子までどうにか運ばれて行った感じの恐怖の数分間でした。次回はやはり早起き早出と皆が反省。
。自分の体が自分で制御出来ないまま八王子までどうにか運ばれて行った感じの恐怖の数分間でした。次回はやはり早起き早出と皆が反省。 袋が無いときついかもしれません。高所恐怖症や鎖場に慣れて無い方は、巻き道あるので心配はいりません。
袋が無いときついかもしれません。高所恐怖症や鎖場に慣れて無い方は、巻き道あるので心配はいりません。